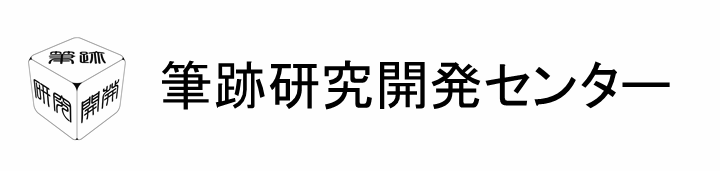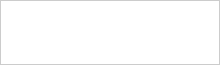江戸時代に藩医、儒学者、博物学者として活躍した貝原益軒をご存じでしょうか。
貝原益軒の数多くある著書では「養生訓」が有名ですが、その他作品、教育論が綴られた「和俗童子訓」には、“古人、書は心画なりといへり、心画とは、心中にある事を、外にかぎ出す絵なり。”と記されていて、その中にある“書は心画なり(書は筆者の人となりをあらわす)”は、古くからいわれてきた言葉で、この考えは現代にも語り継がれています。
「筆跡」と「こころ」の関係
私たちが日々おこなっている筆跡鑑定は、書き残された文字にある特徴の違いを明らかにするもので、筆者の人となりを明らかにすることとは別ですが、文字の特徴の一致や不一致を取り上げるには、文字を書いた筆者の個性をとらえることが必要で、それが筆跡鑑定を進めるにあたって重要となる場面もあります。
それはなぜか?
文字にはそれぞれの特徴がありますが、それは文字の個性であり、いいかえれば筆者の個性が文字に表現されているからで、これが前述の“書は心画なり”とつながっていきます。
筆跡に表出した特徴を筆跡個性といいますが、書き残された文字の一点一画に表出した筆者の筆跡個性を正しくとらえることで、筆者の識別が正確におこなえるというわけです。
筆跡鑑定に関わる「知・情・意」とは
では、筆跡の個性とはどのようなものか・・。
表題にある「知・情・意」は、知識、感情、意志の意味ですが、文字にはこの3つの要素が表れると考えられています。
ここにある知識とは、筆者に備わる文字の知識です。
例えば、楷書、行書、草書など一つの文字でもそれぞれ書き方が異なりますが、文字は筆者が身につけている書の知識の範囲で記されます。
続いて、感情についてですが、これは文字に表れる筆者の感情です。
文字(書き線)の勢いや、リズムなど、筆者の状態が文字に表れますし、体調によって文字のあり方は変化すると考えられます。
そして、意志は文字に表れる筆者の意志で、このように書きたいという筆者の意欲が表れます。
文字は毎度そのあり方が異なり、同じように書こうとしてもある程度変化するものですが、“この線はこの位置にもっていきたい”、また、“この線は長く(もしくは短く)書きたい”など、筆者の意志が伴っています。
実は、この「知・情・意」は人の“こころ”をあらわす三大要素でもあり、文字を正しく鑑定すれば、全てではなくとも、筆者の“こころもち”を理解できることになります。
逆にいえば、個性の最たるものである“こころ”を正確にとらえれば、筆者の識別も可能になるのです。
バランスの取れた識別が重要
勿論、筆跡鑑定は文字の「知・情・意」を調べるだけでは足りず、外形の違いを正しく識別することが必要です。
しかし、その逆に外形の識別のみでも完璧な筆跡鑑定にはなりません。文字のあり方が変化しても(文字の外形に違いがあっても)、真筆ならびに偽筆を正しく見極めるスキルが鑑定人には必要です。
筆跡鑑定に必要な技術
ここ数年で取り扱った模倣筆跡を振り返ると、数年前よりも模倣の精度が上がっているように感じます。
これはほかでもなく模倣の技術が進歩しているということですが、これ迄の説明のとおり、人が書いた文字の外形を似せて書くことはできても、元字の筆者の“こころ”のあり方までしっかりと把握して、筆跡の本質的な特徴まで似せることは極めて困難であり、ある程度のことはできても完全に模倣することは不可能です。
この観点からも、筆跡の「知・情・意」を理解することは、筆跡鑑定に不可欠です。
最後に・・・
文字の外形を正しく調べ、さらに、筆者が文字を構成する一点一画をどのような「知・情・意」をもちながら形成して書かれたのか・・このような視点と技術(書をよむ力)をもって、私たち筆跡鑑定人は作業に取り組む必要があると考えます。