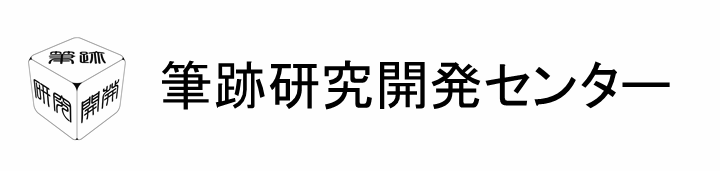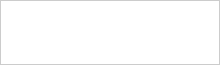世の中には、絵画や工芸品等の美術品の贋作(偽作)が出回っているようで、先月、高知県立美術館所蔵の絵画が専門家の調査によって贋作であると判断されたことがニュースで取り上げられていました。
美術品と同様、偉人・有名人によって書き残された「書」についても、歴史上重要なものを含めて世に出回っていますが、この中にも偽作が含まれていることがあります。
古筆見とは
先日、久しぶりに偉人の書き残した筆跡の調査依頼が入りました。
通常、当センターでは裁判に関わる資料にある筆跡の調査依頼が大半を占め、とりわけ遺言書にある筆跡調査が多いのですが、時に歴史を遡った筆跡鑑定の依頼もいただきます。
「古筆見」をご存じでしょうか?
これは江戸時代からはじまり、明治-大正-昭和にかけて古筆を鑑定する人(職人)を指し、また、古筆をみる行為そのものを指す場合もあります。
「古筆見」の仕事は、調査対象の筆跡が誰によって書かれたものなのか、そして、真筆なのか偽筆なのか・・・、それ以外にも重要なものであれば、その資料が由緒正しいものかどうかについても調査していたと考えられます。
この類の真偽鑑定は、この世のあらゆるものがなくなる日まで続く永遠の課題であり、必須の業務といえますが、現代においては、私たち筆跡鑑定人がこの業務を担っています。
何気なくつかっている「極付き(きわめつき)」や「折紙付き(おりがみつき)」等の言葉は、古筆見が鑑定で用いた言葉で、僅かながら現代にも古筆見の言葉や表現が残っており、われわれ筆跡鑑定人の業務のみならず、現代の一般的なものの見方にも影響を与え続けています。
偉人の筆跡鑑定
依頼のあった偉人が書き残した筆跡の鑑定ですが、これは筆跡鑑定人冥利に尽きる内容のものでした。
と言いますのは、私たちは鑑定をする際、筆跡の運筆や筆致も確認しますので、文字のあり方から筆者の息づかいや心持ち(筆者の個性)に接することができ、さらに、歴史に残る偉人の筆跡ですから多くの場合、文字の書き方が洗練されていて、表現が難しいのですが趣のある文字が多く、日常では目にすることのない特徴が表れているからです。
歴史に残る偉人のパーソナルや筆者の息づかいを感じることによって、その当時の筆者に会えたような…少なくとも、私は筆者に会えたような気持ちになりましたし、一連の鑑定(作業)からロマン(夢)を感じました。
筆跡鑑定は、文字の外形の相違だけで判断するものではありません。それ以外にも、前述した通り、文字の運筆や筆致等、文字の細部にある特徴を入念に調べますが、これらの作業により取上げられたものが筆跡個性であり、ここに筆者の個性が表れます。
偉人に関しては、多くの文献が残されていることがあり、その場合は筆跡のあり方から取り上げた筆跡個性と照らし合わせることができますし、詳細な人物像が残されていない場合は、人物像を補足することも可能です。
最後に...
ご依頼の内容は筆跡の真偽鑑定であり、筆者の個性は直接関係がありませんが、このような作業は心躍るものです。
このご依頼者様を含め、同様な案件のご依頼者様数人のお話によると、古い書物にある筆跡の調査は現状、依頼できる業者がかなり少ないそうで、やっと依頼先を見つけたというお話も伺いました。
書に関しての知識(例えば、書き崩した行書や草書の解読など)をもたない筆跡鑑定人もいますので、その場合、古筆の鑑定をおこなうことは難しいでしょう。
古美術商の方や古書のコレクターの方で筆跡鑑定(真偽鑑定)についてお困りの際は、どうぞ当センターまでお問合せください。鑑定の可不可や筆跡鑑定の料金など、詳しくご説明いたします。